

![]()
![]()
アナログで音出しの先端にあるのがカートリッジですがその種類は千差万別、はいて捨てるほどあります。
コイルやカンチレバーの材質を手を変え品を変えて次から次に新しいものが出てきて、素材が銀線、OFC,
8N など高特性をうたったものが氾濫していますが、この特性重視がどの程度音質に効果があるかは疑問
です。国産カートリッジは特性志向で振動系の軽量化に走るあまり、画一的に音が細く、硬く、冷たい音
になりいくら特性が良くても感動がわく音にはなりません。音場再現の面から説明の余地なく論外。
特性が良くなくてもオルトフォンのようなカートリッジを作ってもらいたいものです。
’オルトフォンの音’を参照。
音の柔らかさを優先するのは音質の3要素を出すための必須条件です。
過去に国産、海外カートリッジを 40種程度試聴。オルトフォン(MC)にかなうものはありませんでした。
試聴した国産カートリッジ(MC、MM):
DENON(8)、A.テクニカ(4)、FR(2)、SAEC(2)、YAMAHA(1)、
SUPEX(1)、ENTRE(1)、MICRO(3)、SATIN(1)、GRACE(2)
試聴した海外カートリッジ(MM):
スタントン(3),エンパイア(4),グラド(2),ピッカリング(2),エラック(4)
オルトフォン(3)
自分のシステムに合うカートリッジを見つけるにはある程度試行錯誤で変えてみる以外にありません。
カートリッジはアンプよりもスピーカーとの相性が優先されます。クラシックは欧州系、ジャズは米国系
とスピーカーの使い分けが一般的です。クラシックとジャズでは奥行き感、ホール感、ライブ感が逆です。
このためカートリッジを使い分ける必要があります。
通常のシステムにハイグレード用のカートリッジを使った場合:
SPUマイスター、りファレンスを例に挙げると高域が粗くなりアンプの欠点が極端に出ます。MC-20
の方が音が滑らかでオルトフォンの特徴が良く出ます。
’価格の高い方が音質が良いはず’という通説が間違っている証明です。但し、特性は良い。
システムのグレードに合ったカートリッジを選定するのが重要です。
![]()
MCカートリッジは出力電圧0.2mⅤ前後と低く、昇圧トランス又はヘッドアンプが必要となります。
カートリッジの純粋な音質ではなく、昇圧トランス又はヘッドアンプを通した音を聴きますのでその
音質に左右されます。選択に要注意。構造が複雑で高価。
MCカートリッジは帯域がフラットで繊細な音質が特徴。特に弦楽器の再生は素晴らしくクラシック
には良く合います。反面、パンチ力には欠けるためジャズには物足りなさが残ります。
MMカートリッジは出力電圧3~5mVと高く、昇圧トランスが無くとも再生できます。構造が簡単で使い
やすく安価で針交換が出来ます。
音質はパワフルでダイナミック。繊細さ、奥行き感には欠けますがジャズ、ボーカルには合います。
シュアⅤ15シリーズ& M3D,7D、エンパイア4000シリーズのようにMMカートリッジでMCのような
繊細な音質もありクラシックにも合います。
![]()
MCカートリッジは出力が0.2mVと低くこのままでは音量が確保できません。必ず昇圧トランスまたは
ヘッドアンプで昇圧する必要があります。昇圧は10~20倍程度。アンプのボリュームで微調整。
昇圧トランスでは入力側のインピーダンスと出力側のインピーダンスの差が昇圧比となります。
’インピーダンスの問題’を参照。
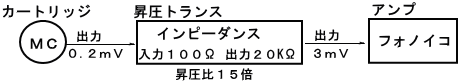
![]()
大編成(オーケストラ)と小編成(室内楽)とでは音の再現に若干の違いがあります。前者はホールの
残響が大きく影響してこれが再生できないと薄っぺらな音になります。後者は楽器が少なく残響再生は
それほど必要なくて、弦楽器は少しきつめに聞こえます。
使用装置:(試聴室の通常のシステム:商品チェック用)
スピーカー :B&W CM1+純正スタンド FS700
カートリッジ :MC-20、M3D
プレーヤー :トーレンス TD-206
管球アンプ :LUX-SQ5B改(出力管GE/6BQ5-PP・8W)
昇圧トランス :DUKANE3A55
ライントランス:WE111C、UTC
フォノイコ :外付けMarantz7型
B&Wのスピーカーはカートリッジに敏感ですので選定に要注意。
B&WとGEバリレラ(MONO針、ステレオ針)は相性が悪い。
推奨のカートリッジは以下。スピーカーとの相性によって選択が変わります。
1.通常のシステム
・オルトフォン:SPU、MC-30、MC-20 →初期型。
・シュア :V15Type Ⅱ、Ⅳ →MC-20 に似た音質。
・シュア :M3D、M7D、M8D →SPU に似た音質。
・エンパイア :4000D(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) →V15Type Ⅳ に似た音質。
試聴室ではMC-20、M3Dを使用中。
1)MC-20 (ステレオ針)
伸びの良い音場感ある音で繊細な表現が素晴らしい音質。
オルトフォンの初期型アームにMC-20 を付けて一度は聞きたいものです。これは驚愕です。
ピアノの響きと弦楽器の絹のような肌触りは聴いた者にしか分からない悪魔の音です。
システムによっては中域の張り出しが薄く貧弱な音質になります。昇圧トランスの選択に注意。
針圧は 1.5~2g(MC)
2)M3D、M7D、M8D(ステレオ針)
ジャズにも合いますが、クラシックでも驚異的な再生をします。
バッハのオルガン、リストのダンテ交響曲、シュトラウスのツアラトウストラなどやピアノ曲、
金管楽器、パーカッションの楽曲ではオルトフォンよりも中域が厚く迫力ある再生。
・M3D('59年):帯域がフラットに近く、色付けのない音場感ある音質。
・M7D('59年):中域に膨らみがあり音の厚みが増加。M3Dより迫力がある。
・M8D('59年):M3D と M7D の中間の音質。入手困難。
いずれも針圧は 3~5g(MM)
2.ハイグレードのシステム
SPU ゴールド以降のモデル(ロイヤル,マイスター,リファレンス,ゴールド)
特性にこだわらず他に類を見ないほど音場感に優れたもので’音質の3要素’も兼ね備えて
います。カートリッジの最高峰。 現行SPUは音質が違うので要注意。
オーケストラ、室内楽、ソロなど全てに対応して音場感も次元が違います。
昇圧トランスで音質が大幅に変わりますので選択には要注意。
国産トランスは音場感が出にくく論外。
SPU クラシック以前のモデルはダンパーが硬化した物があり、要注意。
特性を重視した市販のカートリッジは押しなべて音が細く硬い。材質を変え計測器では達成
できてもその高域が最も重要な中域に悪影響(音が痩せる)しています。
20,000Hz 以上の音は不要。
![]()
レコード録音の年代で再生方法が異なります。
年代の古いレコードと新しいレコードでは録音の特性が違いますので再生の仕方が異なるのが当然です。
古いものは古いもので新しいものは新しいものでが鉄則。
50~60 年代のレコードでジャズ、ボーカルを鳴らすには当時の雰囲気を表現するのが大事です。
例えば当時のジュークボックスの再現。響きのある低重心で図太い音が周りに拡散していく様子が必要
です。これに該当するカートリッジは限定されます。
使用装置:(試聴室の通常のシステム:商品チェック用)
スピーカー :JBL4301
カートリッジ :シュアM3D、GEバリレラVR22(ステレオ)
プレーヤー :トーレンス TD-206
管球アンプ :LUX-SQ5B改(出力管GE/6BQ5-PP・8W)
昇圧トランス :DUKANE3A55
ライントランス:WE111C
フォノイコ :外付けMarantz7型
推奨のカートリッジは以下。スピーカーとの相性によって選択が変わります。
1.50~60年代のジャズ の場合
この年代のレコードでは 1000~6000Hz(ボーカルは~8000Hz) 近辺の中域音の厚みが重要で
この厚みが音を前面に出し奥行き感が出ます。
特性がフラットなカートリッジでは中域が薄く音が痩せて聞こえて必要な迫力が出ません。
1)通常のシステム
・GEバリレラ:RPX、VRⅡ(MONO針)、VR22(ステレオ針)→ 音のパンチ力
・シュア :M3D、M7D、M8D(ステレオ針) → 音の柔らかさ
試聴室では VR22、M7D を使用中。
(1)GEバリレラ(MONO針、ステレオ針)
50~60 年代のジャズ、ボーカルの再生で JBL/ALTEC 等のジャズ用のスピーカーとは
よく合います。
GEバリレラ(MMモノラル)には RPX、シングルバトン、VR2 の3種類があり針の太さ
で音質が違います。針も 0.7ミル、1ミル、3ミル(SP用) があります。
GEバリレラVR22(MMステレオ)はステレオ仕様で、針も0.7ミル、1ミルがあります。
どちらも持っておきたいカートリッジの一つです。
いずれも針圧は 4~5g(MM)
MONO針
針が特殊なバリレラ構造。小編成のジャズで特にサックス,ペットの再生が素晴らしい。
楽器の定位は明確でモノラルにもかかわらず他に類を見ない音場感があります。
音はクリアで厚みと響きがあります。当時のホットな雰囲気を再現します。
ボーカルはバックの演奏から浮き出て、前面に出てきます。
VR22(ステレオ針)
音質はモノラルと同じ傾向ですが音場感は数段上です。歯切れのよい音は逸品。
サイドワインダー(ブルーノート/ステレオ盤)ではリーモーガンのトランペット、
ヘンダーソンのSAXが鮮烈。ヒギンズのドラム、クレンショウのベースは埋没すること
なくはっきりと聴き取れます。奥行き感が明確。
(2)シュア M3D、M7D、M8D(ステレオ針)
50~60 年代のジャズ、ボーカル(モノラル盤、ステレオ盤とも)を再生するにはこれ
らのカートリッジは JBL/ALTEC 等のジャズ用のスピーカーとはよく合います。
音の重心が低く中低域に特徴があります。当時の雰囲気をよく再現しボーカルやサックス
などは逸品。ボーカルのバックの弦楽器再生は滑らかな音質でGEバリレラと違う点です。
通常のシステムには最適。初期型SPUに似た音質。
カーメン・マクレーのサティンドールではベースソロの弦のうなりが生のように聞こえて
きます。ビリーホリデイのボーカル(ステレオ)は古い録音にもかかわらずギター,ピアノ
サックスとドラムのブラシが明確に分離されて再生最近の装置のような薄っぺらな音では
なく音に厚みと温度があります。中域の押し出しと滑らかさは他のカートリッジにはない
もの。楽器の定位も十分で音場感がある再生。
V15 シリーズとは対照的。ジャズには V15TypeⅢ が定着しています。
V15 は特性が良くきれいな音ですがジャズのホットさが出ず、50年代の雰囲気はない。
・M3D('59年):帯域がフラットに近く、色付けのない音場感ある音質。
・M7D('59年):中域に膨らみがあり音の厚みが増加。M3Dより迫力がある。
・M8D('59年):M3D と M7D の中間の音質。入手困難。
いずれも針圧は 3~5g(MM)
2)ハイグレードのシステム
(1)SPU:CG(A)25D、CG(A)25Di(MC/MONO針)
MONO カートリッジの中では最高峰。中でも初期型 25D は他を寄せ付けない音質。
最近の装置のような薄っぺらな音ではなく音に厚みと温度があります。
中域の押し出しと滑らかさは他のカートリッジにはないもの。
楽器の定位も十分で音場感がある再生。
(2)SPU-マイスターなど(ステレオ針)
SPU ゴールド以降のモデル(ロイヤル,マイスター,リファレンス,ゴールド)ではジャズ
でも音の次元が違います。音場感に優れ、小編成のジャズ,ビッグバンド,ボーカルなど
全てに対応して音場感も次元が違います。現行SPUは音質が違うので要注意。
奥行き感では GEバリレラとは音の傾向が違います。
昇圧トランスで音質が大幅に変わりますので選択には要注意。国産トランスは不可。
なお、録音の悪いレコードでは高域で録音の粗さまで再生してしまう場合があります。
2.70年代以降のジャズ の場合
70年代以降になると高性能な録音、再生装置やデジタル録音の出現でレコードの概念が激変。
高音質のレコードを再生するには前項のようなカートリッジでは十分な音質を確保できません。
前項のクラシック用のカートリッジに近い音が適しています。
1)通常のシステム
・オルトフォン:SPU、MC-30、MC-20 →後期型。
・シュア :V15TypeⅢ →(純正針)交換針は音質不可。
・シュア :M3D、M7D、M8D → SPU に似た音質。
・GEバリレラ :VR22 →バリレラMONOと同質の音。
・エンパイア :4000D(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) →V15Type Ⅳ に似た音質。
試聴室では M7D、VR22 を使用中。
M3D、M7D、M8D(ステレオ針)
オルトフォンよりも中域が厚く迫力ある再生。
’ボヘミアの森から’ではイルカのボーカルが出た瞬間、そのリアルさに息を呑みます。
フランクプールセルの’ミスターロンリー’ではゆっくりと流れるテンポの中で大編成の
弦楽器群が出す絹のような音はダンゴにならず全楽器が聞き取れるようです。
GEバリレラVR22(ステレオ針)
JBL/ALTEC 等のジャズ用のスピーカーとはよく合います。
シュアよりも帯域が若干フラットのため高域の再生が若干強くなります。
和ジャズ’鈴懸の径’では鈴木章治のクラリネットが浮き出て迫力があり、ギター,ヴァイブ、
ピアノ、ドラム、ベースもはっきりと聴きとれ埋没することがない音場感があります。
JBL4301はドンシャリ型ですが、日野皓正のトランペット、松本英彦のサックスなど音の出方
が鋭く目前で聴いている雰囲気。VR22とはベストマッチ。
ボーカルの弦楽器の再生ではアッテネータ又はアンプで高域を調整。
2)ハイグレードのシステム
SPUゴールド以降のモデル(ロイヤル,マイスター,リファレンス,ゴールド)では
ジャズでも音の次元が違います。音場感に優れ、音質の3要素を備えています。
ハイグレードのシステムには必須のカートリッジ。現行SPUは音質が違うので要注意。
小編成のジャズ、ビッグバンド、ボーカルなど全てに対応して音場感も次元が違います。
昇圧トランスを併用する場合は使うトランスで音質が大幅に変わりますので要注意。
カウントべーシーなどのビッグバンドの再生は小編成のジャズとは異なります。クラシック
と同じホールでの残響がありこの再生に苦労します。弦楽器はなく、全てがブラス編成のため
音の響きが全く違います。
3.ベースの弦のうなり再生
小編成ジャズ(トリオ、カルテット、クインテット)でベースの再生音はソロを聴けば判り
やすい。弦をはじいた時の弦のうなりが胴体で拡大され聞こえてきますが、その聞こえ方が
カートリッジによって違いがあります。
使用したソース:カーメン・マクレーのサティンドール
使用したSP :JBL 4301
・SPUリファレンス :95点。弦のうなりが明確でも少し軽い。MCの特徴。
・GEバリレラVR22:90点。弦のうなりに’ボンボン’音が少し乗る。
・シュアM3D、M7D:95点。最も生に近いうなりがする。’ボンボン’音はない。
・シュアV15-Ⅱ、Ⅲ:90点。思いのほかうなりを忠実に再生。
・マイクロ M-2100:75点。うなりが少し軽い。国産の中では最もジャズ向き。
・デノン DLー103 :50点。うなりのようなものは聞こえるが、奥行き感がない。
![]()
1.針圧設定
カートリッジの針圧は型番で違いますが、その針圧で音が若干変化します。
軽針圧:1.5~2.0g(通常のカートリッジ)
重針圧:3.0~4.0g(オルトフォン SPU)
重針圧:3.0~5.0g(モノラルカートリッジ,GEバリレラ,シュアM3D~M8D)
新品のうちは既定の範囲で問題ありませんが、20~30年経過した古いものはダンパーに硬化
が見られ、針圧が軽いと音が割れる場合があります。基準より 0.5g程度重くします。
2.情報の氾濫
オーディオ専門の雑誌などにある数多くの論評はメーカーの宣伝をそのまま掲載したもの、
または売るための論評がほとんどで信用できません。データで高特性を謳ったものは注意
が必要です。自分のシステムに合うとは限りません。
特性が変わったものを聴くと先入観で音質が良くなったと思い込みます。しかし10日ほど
聞き込むとほとんどのカートリッジは感動が消えて”?”になります。